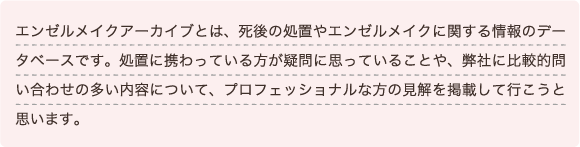
長沙民政職業技術学院 遺体管理学教授 伊藤 茂 氏
見ること
同じものでも見る対場や対象、見るヒトにより「見る」字の意味合いは変化する。
ご遺体を見る場合では警察や海上保安庁、刑務官や警務隊等の司法機関や検事がご遺体を見る場合は「検視」と表され、医師(監察医や警察医を含む)がご遺体を見る場合は「検死」と表される。
検視官とは司法機関の者であり、検死官となれば医師資格を有する者と分類される。
また、医師が行う検死を「検案」と呼び、通常は死後にご遺体を見て作成する診断書を「死体検案書」とされている。
通常、病院や在宅で患者さんが死亡した場合は、生前から患者さんを診ているために「死亡診断書」を作成するが、DOA状態や社会死状態で病院に搬送された場合や変死の場合は、「死体検案書」となる。
東京23区内では勤務医や開業医が死体検案書を発行することは通常では考えられないが、地方都市や地域によっては警察医以外の勤務医や開業医でも死体検案書を発行する場合もあるようである。
医師がご遺体を見る場合は、ご遺体の身体を調べ病状や死因を判断することから、診るとの表現を用いることが出来る。
しかし、診るとは患者さんの診察を指す意味であり、ご遺体を見る場合は治療等を伴わないために、検や調との表記がふさわしい様に思える。
ただし、診察の英語表記は medical examinationであり、監察医を medical examinerと訳していることから、「診る」との表記も間違いではない。
ちなみに東京都監察医務院はTokyo Medical Examiner’s Officeである。
見るとは単純なことではなく、漢詩の中にも風景を見て作ったものがあるが、対象となる山や海により「観山看海」との言葉がある。
山を見る場合は観、海を見る場合は看。本来の「看」とは非常に意味深いものである。
ご遺体を看ること
ご遺体を看ることは、見るや観る、診るや視るとは全く異なる目的がある。
前述のように診るは医師等が死因の判断のためにご遺体を見る行為であり、視るは司法関係者が犯罪等の関係からご遺体を見る行為である。
見るはご家族や葬儀社であり、観るは人体標本や事故現場の通行人等である。
看るとの言葉には、五感を使って認知することとケアをすることが含まれており、診察の診断や治療の様に、目的を持ってみることに加えて対処することも含まれている。
そのために、病院や在宅では患者さんを看ることと看取ること、そしてご遺体に対するケアが「最後まで看ること」となる。
大規模災害等では法令・条例により看護師が被災ご遺体のケアをすることが定められており、これらの場合は死後発見のご遺体も多く患者さんではないが「ご遺体を看る」ことが求められる。
医師がご遺体を診る場合は死因の判断のためであり、その後のご遺体のケアを行う医師は国内においては非常に稀である。
大規模災害時やパンテミック発生時にも医師は診断と治療、または死因の確定にのみ専従し、ご遺体のケアは全てが看護師の業務とされている。
そのために、看護師の「ご遺体を看る」意味は非常に奥深く多岐にわたる。
「看ること」とは、患者さんやご遺体の社会的立場や貧富等に左右されず「すべてのヒト(患者さんやご遺体)」に行われる行為であり、常にリベラルでなければならない。
ご遺体を看ることは患者さんを看ることと大きな違いはない。
特に入院中の患者さんや在宅でケアをしてきた患者さんの場合には、対象である患者さんの心臓死を確認し法令的に死亡していても、看ることの意味で違いは然程ない。
患者さんとご遺体では看る技術は異なるが、看る気持ちには変化は生じない。
そのために、見てこられた患者さんが死亡しても、死亡宣告によりご家族への態度や対応を変えることは好ましくない。
その意味でも、ご遺体やご家族への「声かけ」は重要な行為である。
すでに死亡しているご遺体に対して声をかけても医学的には意味はないが、「髪の毛を洗ってきれいにしましょうね」などの言葉をご遺体にかけながら処置を行うことは、非常に重要な意味を持っている。
声かけの効果
ご遺体に対して声をかける行為は、理論的にも論理的にも医学的意味はない。